成果物がないと魅力が語れない──そんな分析、もうやめませんか?
就活や受験をきっかけに面接対策やES作成で使うからやってみた、くらいの人が多いでしょう。
自己分析ってぶっちゃけ難しくないですか?
僕も強みらしい強みがなくて苦労しました。
しかし、社会人になって気が付きました。
学生時代の成果は努力の証明になりますが、人間性の証明にはなりません。
そこで、僕は人間性の自己分析に特化した自己分析を考えました。
これを「中身勝負型自己分析」と呼びます。
僕オリジナルの自己分析を簡単にするテンプレートを紹介します。
まず、自己分析に対する僕の考え方を紹介します。
基本的には、自分の過去→現在→未来をまとめるのが自己分析です。
ですが、過去と現在を比較してしまうとうまくいきません。
自己分析は過去の自分の立場になって考える必要があるからです。
強み弱みは、子供のころの自分にできなくて大人の自分ができることを書く欄ではないのです。
自分の理想像へのロードマップの過程で自分がどこに位置するかを客観視して、
足りない部分や目標を超えた部分を見直す機会のようなものなのです。
一般的な自己分析は、成果物に応じた結論先行の自己分析であり、自己分析結果よりも成果をアピールするための自己分析になっています。
つまり、年相応の成果が常に求められるため、一度の失敗で魅力が半減する可能性がある。
もっと言うと一般的な自己分析テンプレートは強い成果のない人間がやったところで、
より強い成果を持つ人間に負け確の勝負を挑むようなものなのです。
そこで、同じ土俵に立たない自己分析が「中身勝負型自己分析」です。
🧩 哲学型自己分析テンプレート(⑤⑥は省略してもOK)
① 理想モデルの設定
② 現状の自分とのギャップ確認
③ 強みと弱みの対称整理
④ 社会・他者の中の自分を客観視
⑤ 分析結果のメタ認知(AI利用推奨)
⑥ 分析結果を次回の自己分析のテーマにする(分析結果を結論にしない一工夫)
① 理想モデルの設定(過去の自分が持っていた理想像の仮設定)
今回分析する対象は何か?(例:性格、行動、思考パターン)
その対象について、自分が理想と考える最高の基準や状態は何か?
抽象的な例:「全知的な理解力」「完全な自己統制」「超人的な集中力」
具体的な例:「○○さん」「○○先輩」
② 現状の自分とのギャップ確認
現在の自分は、その理想に対してどこまで到達しているか?
到達していない部分はどこか、なぜそこに届いていないと感じるのか?
③ 強みと弱みの対称整理
この対象について、自分の強みは何か?
その強みの裏返しとして生じる弱みは何か?(対義語ではなく強みを実現している構造的に考える)
構造の例:論理力は無理ない筋道を立てて物事を考えられること。(青文字が構造の部分)
反面、他人の論理を理解する努力が必要。
強み→弱みの例:「論理力 → 他人の論理に疑問を持ちやすい」「独立性 → 協力の機会が少ない」
弱み→強みの例:「人よりも細かいことが気になる→担当していることについて確実な説明ができる」
④ 社会・他者の中の自分を客観視
この対象に関して、自分は社会や集団の中でどんな位置にいるか?
多数派か少数派か?→協調性をどう発揮していくか
ズレや摩擦はどこに生じているか?→コミュニケーションで気を付けていること・気を付けること
その立ち位置に価値を置いているか、それとも問題視しているか?→伸ばすか・改めるかの方向付け
⑤ 分析結果のメタ認知 (自分の認知を認知する→自分の認知はどこから来たのかを知ること)
ここまでの分析を振り返り、「自分の分析傾向」や「分析そのもののパターン」に気づいたことを整理する。難しいときは、ChatGPTとかのAIに自分の思考の癖を洗い出してもらうと楽です。
例:「単語の意味ではなく、構造的な対称性に着目している」
→「論理⇔感情」ではなく、論理の構造がもたらす不都合を弱みとしている。
例:「理想像とのギャップを比較する手法」→目標と自分の位置の相対化による自己啓発的思考。
⑥ 分析結果をどうするか(分析結果を結論にしない一工夫)
今回の分析で、あえて結論を出さない問いを一つ作るなら?
これは就活等の際に、志望先に行ったらどうなりたいかというビジョンに直結します。
例:「次の理想像の更新はいつにする?」
→長期スパンの目標の再設定。(例:社会人になったらどうなりたいか)
例:「これからの自分に必要な要素は何か?」
→資格や技術など具体的で成果(マイルストーン)となるものを設定する。
🌱 自己分析の書き方
私の強みは③です。
③を強みにした背景は、私がコミュニケーションをとる際に④について意識しているからです。
④を意識している理由は、⑤の考えから自分の考えの傾向(癖)を理解しているからです。
~エピソードは③(強み)の具体的証明として、ここに入れる~
この強みは、⑥の課題を意識することで今後も活かしていきたいと考えています。
~⑥(今後の活用)の部分は志望先の求める人物像と関連させて、ここに差し込む~
こういった点から、志望先に③の強みを提供できると考えています。
__________________________________________________________
※面接・口頭用:要約短縮版(特に⑤を圧縮する)を用意しておくとより良いと思います。
特に⑤は高度な話になるので、時には深堀されるまで隠しておくことも一手だと思います。
__________________________________________________________以下、簡略版。
私の強みは③です。
③を強みにした背景は、私がコミュニケーションをとる際に④について意識しているからです。
~エピソードは③(強み)の具体的証明として、ここに入れる~
こういった点から、志望先に③の強みを提供できると考えています。
__________________________________________________________
こんな感じの口頭verだったり与えられる時間や文字数に応じて何パターンかあると良いです。
そして、文章を削る際は、⑤→④→⑥→①→②→③の順にしましょう。
各要素の重要度の逆順になっています。
重要度は、相手への伝わりやすさと自己分析における深さで評価しています。
深い自己分析を簡潔に伝えることは難しいので、とにかく伝わりやすさを重視してみてください。
深い自己分析は、あなたに何を問われても答えられるという自信をもたらすでしょう。
無理に伝えようとしなくても話し方や姿勢、目線などから相手に自然に伝わります。
知恵や知識と同じで、ひけらかさなくても問われたら答える程度が塩梅です。

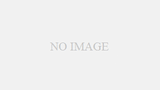
コメント